尿路感染症(膀胱炎や尿道炎、ときに腎盂腎炎)は
頻尿や血尿、痛みの原因となります。
また、解剖(人体の構造)上の特徴から、特に女性では尿路感染症が多いとされています。
多くの人が悩んだことはあるのではないでしょうか。
今回は「尿路感染症を繰り返すことで、なぜ痛みや頻尿などの症状が長く続くのか?」
という疑問は今まで謎でした。
そんな問いを明らかにする論文を紹介した記事がScienceNewsから最近出ていました。Helen Bradsawさんの書いた記事です。リンク貼ります。
Here’s why pain might last after persistent urinary tract infections
Here’s why pain might last after persistent urinary tract infections (sciencenews.org) Mar 1, 2024
記事の根拠論文、その簡単な内容
Recurrent infections drive persistent bladder dysfunction and pain via sensory nerve sprouting and mast cell activity.
Sci Immunol. 2024 Mar;9(93):eadi5578.
- 尿路感染が改善後も痛みや頻尿などの症状が続く原因は?
- マスト細胞、単球という免疫細胞が関与(マウスを使った実験)
- これら免疫細胞が神経成長因子(NGF)を放出する
- 神経細胞の増殖を促進することで、知覚過敏を引き起こす
- その結果、痛みや頻尿の症状が細菌感染が落ち着いたあとも続く
- この研究は将来の治療開発に繋がる可能性がある
この論文から私自身が医師として得られた知見を3つご紹介します。
ポイント①:症状のメカニズムの説明が可能になる
この論文・記事で重要なことのまず一つ目として、
「細菌感染が改善しているにも関わらず、頻尿や痛みが続く」という現象に対して、
患者さんに対してメカニズムの説明が可能になる、ということです。
患者さんは自身の体について、
「症状の原因は何なのか?」
「どうやったらよくなるのか?」
という疑問の解決をするために、病院へ受診されることが多いと思います。
そのような患者さんに症状の原因について説明するときに、「わからない」と言っても納得してもらえませんし、診療の満足度は低くなってしまいます。
正直にいうと、
医療には「症状の原因がわからない」「適切な対処法がない」というものが数多く存在します。
しかし、こういった論文が世に出ることで、患者さんに対して、
症状の原因が何か、なぜ起きているのか、という説明が可能となるかもしれません。
スパっと症状をよくすることは難しいとしても、
どうして症状が続いているのか、少しでも患者さんが自身の症状の原因や理由について理解ができると、不安を多少なりとも軽減させる手助けをすることができるのではないでしょうか。
注意:
今回の論文はマウスを対象としており、ヒトを対象としていないので、必ずしも我々ヒトにも同じことが当てはまるかどうかはわかりません。
ポイント②:抗菌薬による治療はやるなら短くてよい
2つ目のポイントは、抗菌薬投与期間は不必要に長くしなくていい、という点です。
医療者おなじみのサンフォード感染症治療ガイド(私はアプリ版を使っています)では、一般的に尿路感染症は症状がある場合、抗菌薬治療の適応(対象)となる、とされています。
そして、その投与期間は長くても3-5日間であることが多いです。
しかし、その後も症状が続いてしまう患者さんもおり、症状があるからと言って抗菌薬を続けてしまうケースがあると思います。
抗菌薬の治療期間が延長することで、結果として耐性菌出現のリスクとなります。
近年では薬剤耐性菌の出現が問題となっているので、(新しい抗菌薬開発は進んでいない)
いかに短い期間で治療を終えるか?
という考えが重要ですので、症状があっても抗菌薬治療を終えるうえでの一つの参考にはなるかもしれません。
注意:繰り返しですが、今回の論文はマウスを対象としており、ヒトを対象としていないので、必ずしも我々ヒトにも同じことが当てはまるかどうかはわかりません。
ポイント③:薬剤開発のヒントになる
今回の論文では、肥満細胞を働きを抑制したり、肥満細胞の産生する物質を除去すれば、マウスの症状は改善した、と記載があります。
つまり、そこに薬剤開発のヒントがあるということです。
私たちの普段から処方する一般的な痛み止めや、抗ヒスタミン薬では症状緩和に不十分であるため、
こういった症状に悩まされている患者さんに対して、有効な治療の開発が今後進んでくれることを期待したいと思います。
さいごに
ScienceNewsはwebで記事は閲覧できますが、X(ツイッター)のフォローもお勧めです。
時々こういった医療系の話題も取り扱ってくれ、他分野の勉強のきっかけになるので、役立っています。
英語版のみで日本語版はないようなので、医療に関連する記事があれば、その根拠論文と共に自分自身の勉強として今後も記事を書いていこうと思います。
ところで、書いているうちに、トイレ(小)に行きたくなりました。
自宅でこの記事を書いているので、座ってすることにします。
「自宅では座りション」がブログをはじめて1か月たった時点での私の最近のマイブームです。
奥さんに言われたら笑われそうなので、内緒にしておきます。
ブログを通していろいろ勉強になるので
もう少しだけ続けてみようと思います。
おわり

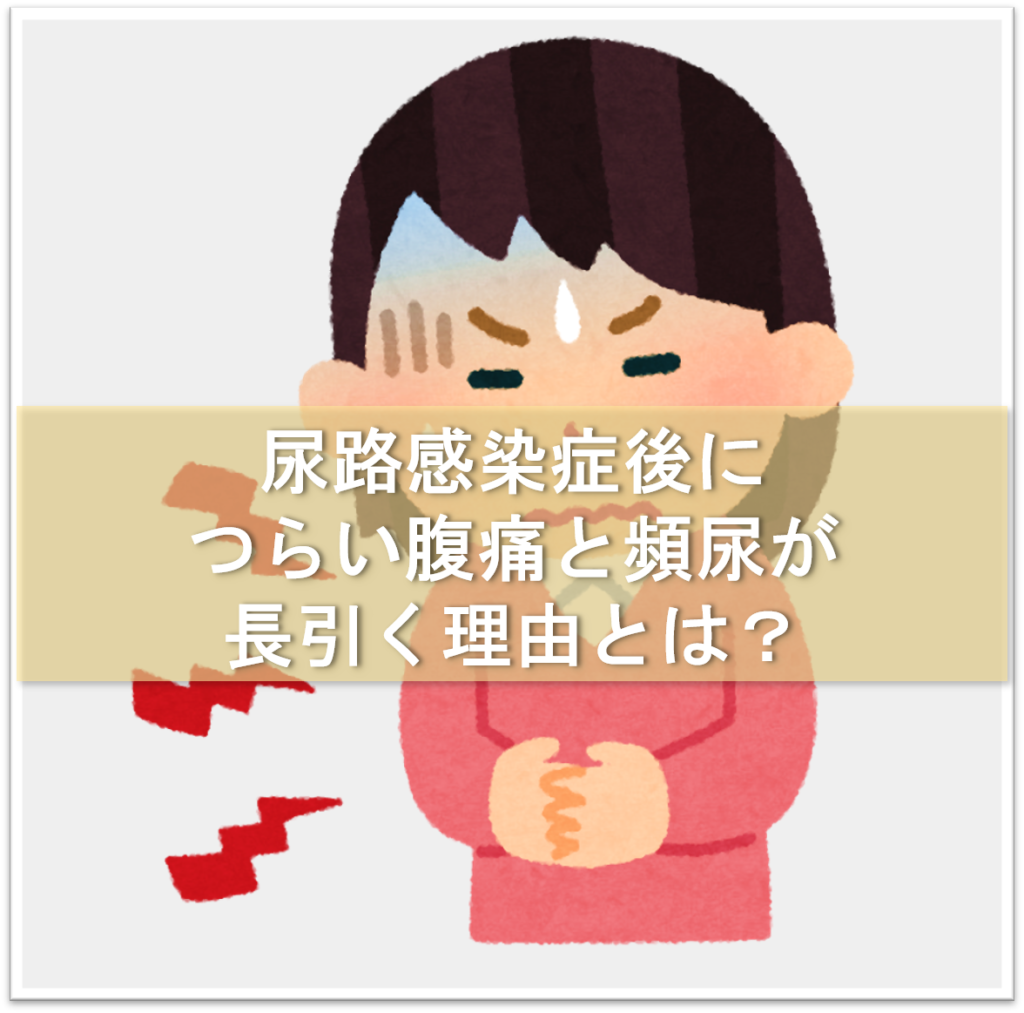



コメント