ロキソニンが認知症リスクを低下させる?
Long-Term Exposure to Non-Steroidal Anti-Inflammatory Medication in Relation to Dementia Risk
Journal of the American Geriatrics Society に掲載された論文*1では、NSAIDsを24ヶ月以上にわたり長期内服した患者において、認知症発症リスクが約12%低下したことが報告されています。この結果は、1991年から約14年にわたって約11,000人のデータを収集・解析したものです。
NSAIDsの中には、アミロイドβ1を減少させる作用を持つものと、そうでないものがあるとする先行研究があり、その分類は Journal of Neurochemistry(2004年)にて報告されており、以下に一覧表を載せておきます*2。
| 分類 | NSAIDsの名称 |
|---|---|
| Aβ42低下作用あり | Diclofenac(ジクロフェナク)Ibuprofen(イブプロフェン)Piroxicam(ピロキシカム)Indometacin(インドメタシン)Sulindac(スリンダク)Flurbiprofen(フルルビプロフェン) |
| Aβ42低下作用なし | Naproxen(ナプロキセン)Rofecoxib(ロフェコキシブ)Nabumetone(ナブメトン)Ketoprofen(ケトプロフェン)Meloxicam(メロキシカム)Celecoxib(セレコキシブ)Phenylbutazone(フェニルブタゾン)Etoricoxib(エトリコキシブ)Valdecoxib(バルデコキシブ) |
今回の研究では、予想と反しアミロイドβを低下させないNSAIDsが認知症のリスクを下げていたことから、筆頭著者のIlse vom Hofe氏らは「抗炎症効果を有する薬剤の長期投与が、認知症リスクを低下させる可能性がある」と述べています。
ただし、この研究はNSAIDsによる認知症予防効果を明確に証明するものではなく、「認知症予防において抗炎症作用が関与している可能性を、実臨床のデータで示唆した」という位置づけで捉えるべきだと思います。
個人的には、NSAIDsのAβ低下作用のある・なしについてはこの論文を読んでから初めて知ったので、驚きでした。
*1 認知症の原因とされる脳内タンパク質のこと。
*2 Journal of Neurochemistry, 2004年
この論文から言えること
今回の論文から言えることは、あくまで「NSAIDsの抗炎症作用が認知症発症抑制に関与しているかも」ということです。詳細なメカニズムはわかっていませんし、もしかしたらCOX阻害以外の何かしらの作用が関連していたかもしれません。
予防的にNSAIDsを長期的に予防的に内服させることは、胃潰瘍などの出血性合併症のリスクにもつながる可能性があるため、議論の余地があります。
しかし、今回の論文をもとにした新規薬剤の開発などが進むことにより、将来的には認知症の発症高リスク患者を対象とした予防薬が出現するかもしれません。
今後の研究に期待したいところですね。

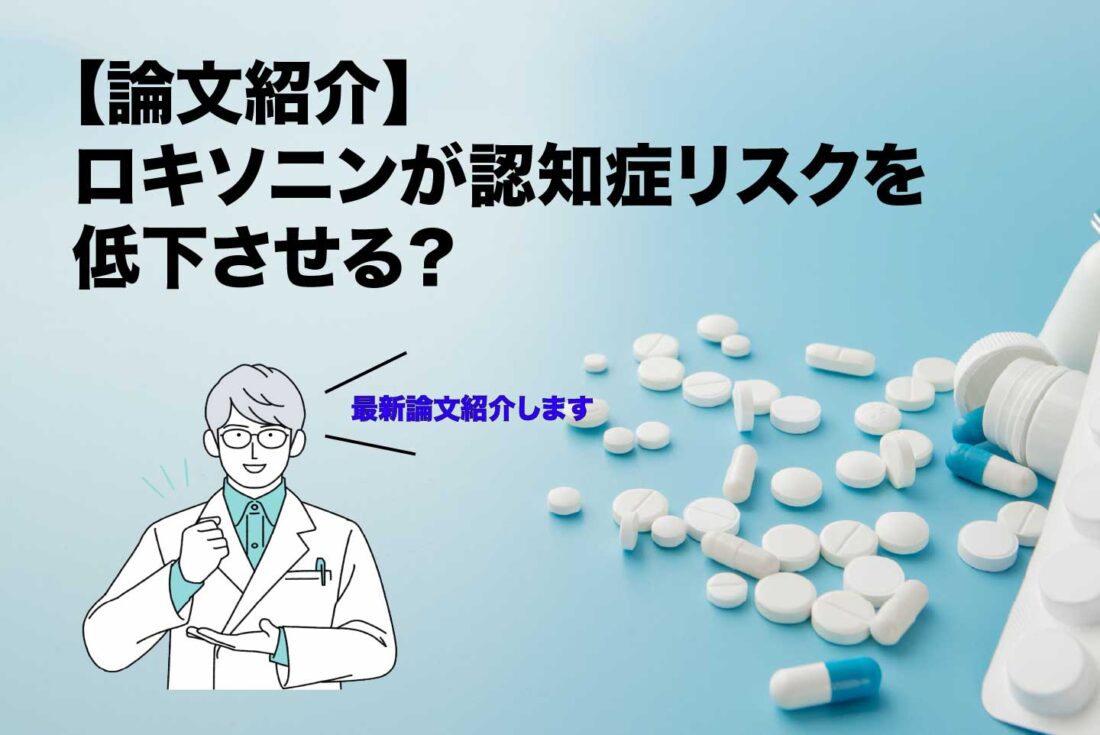


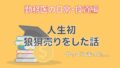
コメント